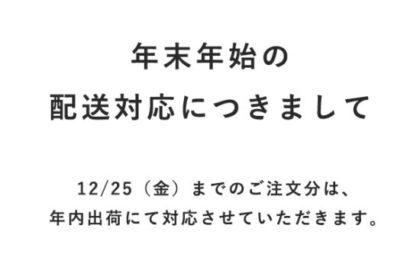愛知県三河地方で、七輪をつくる職人さん、高橋さんにお会いしました
三河地方で黒七輪を製作されている職人さん、高橋さんの作業風景を見学させていただきました。

高橋さんは、大正時代から続く窯元さんの4代目にあたる当たる職人さんです。
瓦つくりをされていたという、高橋さんの窯元さん。
瓦職人さんならではの技を生かし、頑丈でありながら細部にまでこだわりの詰まった、黒七輪をつくっておられます。
瓦つくりの伝統・製法を受け継ぎ、つくり続けられている黒七輪
三河産の黒七輪は内側は珪藻土、外側は頑丈な三河土の二重構造。
高橋さんが製作を仕上げているのは、三河土の外側の部分となります。
耐久性や耐火性に優れた強度ある瓦の土を使って作られるこの七輪は、「一生使える七輪」とも言われています。
とても固い土、瓦にも使われる三河産の土

1枚の板チョコのような、原料の土。土の空気を抜いてぎゅっと固めている、とても固い土なんだそう。

厚みなどにも差があり、少しの違いで仕上がりに差が生じてしまうとのこと。
たった1ミリ以内の差でも、出来上がった製品には、数ミリ以上のズレとなって仕上がりが左右されてしまうそうです。

土を切る道具。おなじサイズに土を切るのに使う道具で、ピアノ線を調節して、土を切っていくのに使うそうです。これも瓦に使う道具なんだそう。
1枚1枚の板のような土を組み立てて、七輪が出来上がっていきます
「1番大変なのは『てつけ』ですね」
分かりやすいように、小さな土で「てつけ」とよばれる組み立てていく工程を再現して下さりました。




1枚1枚の板上の土を、パズルを組み立てるように、手作業で組み合わせて接着させていきます。
土と土とが接着する部分は、削るようにして、傷をつけて摩擦を強くし接着させるそう。
「『かけあぶり』はさんざん悩みました」
細かくかけあぶると、きれいにくっつく。強くかけあぶると強くくっつく。何度も何度も経験して、加減を習得されていったそうです。

土を組み立て一つの製品を仕上げるまでに、およそ1時間ほどかかるそうです。
原料の土を切らせてもらいました

小さいナイフのような道具で切らせてもらいました。1センチ以上厚みのある土。1回では切れない固さで、土の強度を感じました

「戸口は一回で切らないといけない」
空気を送り込む戸口の部分は、一回で切らないといけないそう。とてもきれいな仕上がりは、やっぱり職人技だと感じます。
細部まで瓦つくりの技術をもとに、仕上げられていきます

組み立てられた七輪は、角や断面、表面の仕上げまでを、一つ一つを手作業で丁寧に整えられていきます。

瓦つくりの技が至る所に詰め込まれています。

表面・断面・角まで、どこを見ても、きれいな仕上がりの七輪。大変な手間がかかっています。
土の強さと、技術の細やかさの組み合わせが、とても魅力ある製品だと感じました。
「割れないように割れないように、見る」
「難しい工程などはあるのですか?」との質問に、「割れないように割れないように、見る」と、慎重に答えてくださった高橋さんがとてもとても印象的でした。

かたちが出来たら、乾燥させ、焼成へと製作が進んでいきますが、この「焼くまでに乾かす時間」といううのが、とてもデリケートなようです。

組み立てた七輪を、台の上にのせて、乾かしているところ。1週間ほどの時間をかけて、何度も何度も上下をひっくり返し乾燥させるそうです。

「乾燥させている間に割れてしまう、それを防ぐのが難しい」
「何度も様子を見て、上下をひっくり返す」
「30分前は普通だったのに、少し風に当たっていただけでも割れる」
「おいている場所が少し違うだけでも、乾き方に差がある」
「これだけ手間をかけて、割れるのは悲しい」
乾かすことに関する言葉が、沢山うかがえたのが特徴的でした。
瓦つくりに使われる技と、細部への思いやりの詰まった製作風景。
また、たくさんの手間を注ぎ、慎重に、1台1台の七輪と向き合っている姿が印象的な、職人の高橋さんでした。
インタビュー時の音声をもとに、レポート記事を書いております。
工程の途中に出てくる用語などには、聞き違い等による違いがあるかもしれません。
ご了承いただけますと幸いでございます。